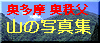今年の夏は、白馬岳周辺の未踏ルートを歩く計画にした。白馬岳は大雪渓もまだ歩いていないのだが、山中で2泊して祖母谷温泉に下山したいので、今回は鑓温泉から時間をかけて登るプランとする。
祖母谷ルートは下りでも8時間くらいはかかるという長大な行程で、歩く人もあまりいない。しっかりした準備と体調管理が大切となる。
通算3度めの白馬岳登山計画として、この長い道を歩くことを第一の目標とした。

雪渓をいくつも越えていくと、上部に鑓温泉の建物が見えてくる
|
●猿倉から白馬鑓温泉へ
8/2(土)
現地の天候が安定せず出発のタイミングが難しい。結局8月に入っての出発となったが、1日か2日は雨や雷に会うのは避けられそうにない。
体力温存のために夜行は避け、夕方に新宿を発車する高速バスを利用する。松本に前泊し、翌朝松本駅からムーンライト信州に乗るという変則的なアプローチとなった。
白馬駅からバスで猿倉へ。ここには初めて来た。猿倉荘の前に臨時の登山案内所が開設されていて、用意していた登山計画書を提出する。「祖母谷に下る人は今日2人めだよ」と言われた。回りは大雪渓を登る登山者であふれ返っているのに祖母谷ルートは2人とは、何とも極端である。
青空の下での出発となる。樹林帯の登りからいったん林道に戻って、大雪渓コースと分かれて鑓温泉への分岐に入る。しばらしてあたりが開けるようになると、白馬岳の稜線が青空の中にくっきりと浮かび上がっていた。ただ雲も多く沸き立ち始めてきて、天気の移り変わりが早いことを示している。
初日は早朝から歩かなくても小屋には着けそうだが、この日は午後の天気が怪しいので、早めの行動を心がけた。また、槍温泉小屋のテント場が狭いことも早発ちの理由のひとつだ。テント場はどこでも、あまり到着が遅いと傾斜地しか残っていないことがある。テントは平坦な場所に設営することが安眠の必須条件である。
シモツケソウやオオバギボウシなどの花が多く見られるようになると小日向(おびなた)のコルに着く。一帯はタテヤマウツボグサやニッコウキスゲも咲き、ちょっとしたお花畑になっている。
コルとはいっても白馬鑓ヶ岳から派生する双子尾根の一端であり、ここからは尾根から離れてやや下り気味の道になる。急な所はなく、花の群生している平坦道を通過していく。稜線を見上げると、いく筋もの雪渓が日の光を受け、眩しいくらいだ。
残雪の斜面を数回通過するが、いずれも山腹のトラバース道で危険はない。雪上を駆け抜ける風が夏の熱気を和らげてくれる。雪渓と雪渓との間の潅木帯にキヌガサソウ、サンカヨウの白い花を見る。
大雪渓コースほどではないにせよ、この登山道も夏の暑い日には随所で天然クーラーの恩恵にあずかることができた。4度めの雪渓は登りがある上に比較的長距離を横断するので、若干気合が入る。やがて上部に鑓温泉の建物が見えてきた。
雪渓を下りて、雪のない沢筋を横断する。振り返ると、渡ってきた雪はまだ2m近くの厚さがあるのがわかった。
最後の急登を経て、白馬鑓温泉に到着する。
こんな雪渓の斜面に温泉付きの山小屋が建っているとは驚きである。プレハブ造りの建物は夏の営業期間が終わると解体し、また次の夏に組み立て直すという珍しい山小屋だが、こんなところに建つ建物ならそれもわかる。
テント泊申込みの際、温泉に入りますかと聞かれたので、入りますと答える。ここに泊まる人で温泉に入らない人っているのだろうか。テント設営代と込みで1200円だった。
白馬の稜線は見えないが、東側に焼山、火打などの頚城山群、また信越の高妻山などがよく見える、眺めのいい場所である。さっき越してきた小日向のコルと小日向山も真正面に見えている。
鑓温泉小屋の建物をよく見ると、プレハブのパーツに「売店下の壁」などと位置を示す文字が書かれている。要するに、夏の終わりに小屋を解体した際、建材は下界に運び下ろして、翌年また同じ位置にそれぞれの建材をはめ込んで小屋を再建する、という作業を毎年繰り返しているのだろう。
だから壊して作り直しても、また同じ形の小屋ができるのだ。
眺めのいい露天風呂は硫黄臭が強い白濁のお湯で、満足度は非常に高い。テントを張った後はもう食べることくらいしかやることがないので、ゆっくりと湯に浸かった。
なお露天風呂は混浴で、女性用の内湯が別にある。また、露天風呂が女性専用となる時間は20時から1時間だけだった。ずいぶん遅い時間のような気もするが、露天風呂は登山道やテント場から丸見えなので、それもしょうがないだろう。
それにしても、この野外ステージのような丸見えの露天風呂でくつろぐ男性諸氏(特に高年登山者)のデリカシーのなさは目を覆うばかりだ。山を楽しむ女性がこのところ急増してきたことを考えれば、もう少し周囲に気配りをして、大事なところは隠して入浴しないと駄目である。
そうでもしないと、この野趣あふれる露天風呂も、そのうち水着着用が必須になってしまうことだろう。
夜半、雨が降った。降りは強く山頂付近で雷も鳴ったのだが、それほど長い時間ではなく、夜中には満点の星空となった。