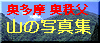●白馬三山を縦走
8/3(日)
2日目の朝、一面の雲海と朝焼けで始まる。高妻山の左から昇る真っ赤な日の出を拝む。
白馬の稜線に向けて
鑓温泉小屋を出発。昨日の緩やかな登りから一転、最初から厳しい急登が続く。振り返ると山肌の緑と雪渓の境に建つ鑓温泉小屋が朝日を受け、なかなか絵になる。

白馬鑓ヶ岳から杓子岳(右)、白馬岳(中央)に向かう
|
高度を上げていくとにわかに岩場が増え、長い鎖のついた岩上の登りとなる。
ところどころ水が染み出して岩が濡れているので、スリップしないように注意する。鎖場は思いのほか長く、特に下りの場合は慎重さが要求されるところだ。「昨年滑落事故があったので注意」との看板がかかっていた(後日知ったが同じ日の午後、下山中にここから雪渓に落ちた人がいたらしい)。
緩くなった場所で一休みする。左手に森林限界上の伸びやかな稜線が見え、小屋が建っているがどのあたりだろう。唐松岳・八方尾根上の小屋だろうか。
長くつらい登りがひと段落すると、あたりが開けた気分のいい湿原状の場所に出る。大出原である。突然出現する大きなお花畑は圧巻であった。チングルマ、コイワカガミ、ハクサンコザクラ、アオノツガザクラ、ウサギギク。湿性の高山植物が咲き競うほか、ミヤマキンポウゲやハクサンイチゲと、白馬の稜線を代表する花も早くも登場する。ようやく北アルプスの夏山に来た実感が湧く。
右手には白馬鑓ヶ岳から派生してきていると思われる岩峰群がいい景観を醸し出している。稜線から下山してくる登山者と多くすれ違うようになる。
大出原を後にすると、再び急な登りが続くようになる。鑓温泉からはまだ距離的にほとんど進んでなく、今日の核心部はむしろこれからだ。森林限界を超えて暑さから解放されているのが救い。
正面に見上げるアルプスの稜線はすぐに届きそうでなかなか近づかない。カール地形の長い登りを黙々とこなしていく。稜線の上の空はいつの間にか白っぼく変わっていた。岐阜・富山県側の天気はどうなっているのか気になる。
しかしこの登りは長い。高度が上がったぶん見える角度が変わってはいるものの、まる1時間くらいほとんど景色が変わっていない中を登りつづけている印象だ。
上部は砂礫となり、コマクサも見られるようになるとなった。力を振り絞ってようやく稜線に到達する。左手は唐松岳方面の伸びやかな尾根道、これから進む白馬方面は、鑓ヶ岳の白い山体が大きく、まだ高い。
13年前に五竜岳まで縦走したときは逆コースだったせいか、この山の巨大さをこれほど実感できていなかった。この先の頑張りどころに備えて一休みする。
白い巨体目指して再び歩き出す。気持ちのいい稜線を登っていくと、背後には剱岳や鹿島槍といった名峰が姿を見せていた。その右後方には富山湾も。岐阜県側の空はやや雲が多かったが、遠く槍ヶ岳も穂先を覗かせていた。
砂礫の登りは足を取られやすく歩きにくい。山頂に続く踏み跡は何本かあって、登る人と下る人との間での通過待ちはあまり発生しない。
登山者で賑わう白馬鑓ヶ岳山頂に到着。白馬岳、杓子岳や それらを結ぶ尾根筋が伸びやかで素晴らしい眺めである。特に三角柱を横にしたような杓子岳の特異な山容が目をひく。また旭岳や清水岳、さらにその清水尾根上の不帰岳も、今日は特別な存在感を持って見ることができる。
下界は猛暑だが標高2900mの高峰は大陸からの涼しい風が駆け抜けていた。
次は杓子岳へ。白砂の稜線を下っていくとここも、多種多様な花が咲き乱れていた。オンタデやムカゴトラノオが斜面を埋め尽くす光景から始まり、イワベンケイ、タカネツメクサ、イワオウギ、ミヤマダイコンソウ、チシマギキョウ、シコタンソウと次から次へと現れる。
そしてテガタチドリがいたるところに見られるのは北アルプスならではだ。クルマユリのオレンジ色もあちこちで光彩を放っている。ウルップソウはほぼ終わっており、花茎のみが残っていたがその数は非常に多く、開花の時期は壮観だろう。
岩の斜面にはミヤマオダマキ。花弁を下に向けた清楚な姿でおなじみだが、ここでは横または上を向いて咲いている。短い生涯の中で、いち早く昆虫に受粉してもらうための知恵なのか。
鑓ヶ岳に比べて、杓子岳は100m近く低いのだが、縦走路はそれ以上を下ってからの登り返しとなる。13年前は巻いてしまったので、今度は山頂への踏み跡を見逃さないように行く。
杓子岳への登りは急できついが、きれいに花をつけたコマクサに慰められながら高度を上げる。天候も下り坂となり、白馬岳山頂が雲で隠されるようになる。杓子岳山頂部の一角に着き、稜線伝いに山名標のある杓子岳に着く。
日差しはなくなり、白馬岳も鑓ヶ岳も山頂部は雲の中になってしまったが、ここは清水尾根を眺めるのにいい場所だ。不帰岳から先、どこで尾根を外れて長い下りに入るのかを目で追いながら明日の行程を思い描く。
今日の宿泊地、白馬山頂宿舎テント場に向かう。杓子岳から登山道に戻り稜線の登山道に戻る。ここからもさらにひと下りがあり再び登り返す。13年前に抱いた印象以上に、白馬三山の縦走路はアップダウンが激しかった。
あれだけ人で賑わっていた登山道も、いつの間にか静かになった。それでも花は相変わらず多く、イブキジャコウソウ、イワツメクサ、ミヤマアズマギク、タカネシオガマが現れる。今日はいったい何種類の花を見ただろう、3回目の白馬山行は、見た花の種類は今回が一番多いかもしれない。
丸山へ登り返して右手に白馬岳頂上宿舎、そして大雪渓コースからの登山道を合わせてテント場に到着する。鑓温泉からは標高差が大きく大変だったが、ほぼ想定通りの時刻に着くことが出来た。
テントを設営し、空身で白馬岳を往復する。途中、祖母谷温泉への分岐を確認。そちらは大きな雪渓が残っており、シリセードをして遊んでいる人がいたが、歩く人はやはり少なそう。大勢の登山者は白馬岳、白馬山荘方面に向かう。
そして8年ぶりの白馬岳登頂。ガスの中になってしまったが、体の大きい雷鳥がいた三国境から白馬大池方面の稜線方面も真っ白になってしまい残念だ。
今日は、今回の行程の中で一番安定した天候を想定していたのだが、やはり自然には勝てない。岐阜県側の雲が厚いことを考えると、現在九州や四国に大雨を降らせている台風の影響がここ中部日本の山岳まで影響を及ぼしているようである。
温暖化の影響もあるのか、ここ数年の台風は、ちょっと大きめになると日本列島の半分の天気を簡単に崩してしまうくらいの威力を持つことが多い。山行計画を立てる際には、やはり台風の動向に注意が必要である。
白馬岳から下る途中、白馬山荘の裏手に入り、柵で囲われたお花畑を見ていくことにする。コマクサやチシマギキョウが多く見られるが、草むらの中に黒い花が印象的なミヤマアケボノソウが咲いていた。
そして山荘横に下りると、ミヤマキンポウゲの大群落が斜面を黄色く染めており目を見張る。改めて実感した、白馬岳はやはり日本屈指の花の山である。
頂上宿舎に下り、食堂で生ビールとうどんを注文する。山ではいつもは節約して缶ビールだったので、生ビールは久しぶりでうまい。
テント場に戻って、周囲の花を写真に納めながら時間をつぶす。テント場回りの斜面はハクサンイチゲなどの群落がすごかった。ウルップソウも咲き残り、クロユリが見れたのはうれしい。
稜線は終日ガスの濃い1日だったが、今夜も雨となった。前日と違い雷はなかったが、雨粒は大きく、次第にどしゃ降りとなる。降りが弱まった後もシトシトと長い時間降り続け、いつもの山の夕立とは明らかに違っていた。