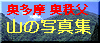| 2019年8月4日(日) | |||
| ◇ | 調布IC | 4:20 | |
| 中央自動車道 | |||
| ◇ | 甲府昭和IC | 5:35 | |
| 国道20号,県道20号,南アルプス街道 | |||
| 6:20 | 夜叉神登山口 | 6:50 | |
| 7:50 | 夜叉神峠 | 8:00 | |
| 9:30 | 杖立峠 | 9:40 | |
| 11:05 | 苺平 | 11:30 | |
| 12:00 | 南御室小屋(テント泊) | ◇ | |
| 2019年8月5日(月) | |||
| 5:10 | 南御室小屋 | ◇ | |
| 5:50 | 2700m地点 | 6:00 | |
| 6:20 | 薬師岳 | 6:35 | |
| 7:10 | 観音岳 | 7:22 | |
| 8:35 | 賽の河原 | ◇ | |
| 8:45 | 地蔵岳 | 9:05 | |
| 9:15 | 赤抜沢ノ頭 | 9:40 | |
| 10:20 | 高嶺 | 10:33 | |
| 11:20 | 白鳳峠 | 11:30 | |
| 13:35 | 南アルプス林道(白鳳峠口) | ◇ | |
| 13:50 | 広河原 | 14:00 | |
| バス | |||
| 14:40 | 夜叉神登山口 | ◇ | |
| 南アルプス街道 金山沢温泉立寄り 県道20号,国道20号 |
|||
| 17:20 | 甲府昭和IC | ◇ | |
| 中央自動車道 | |||
| 19:25 | 高井戸IC | ◇ | |
| Page 1 2 |
曇り、曇り、雨、曇りと続いていた自分の最近の山行記録も、ようやく転換点が来た。テントを背負って縦走した鳳凰三山は、雨や雷とは無縁の完璧なピーカン山行となった。
今年歩いた山は日帰りばかりなので、2泊以上のテント泊は体力的に不安がある。土・日で行こうとしたが、土曜は中部山岳で雷雨予報がある。土曜を避けるとかなりの確率で雷からは逃れられそうだ。ここは休みをとって日・月と行くことにした。
 南御室小屋 [拡大] |
|
まだ歩いたことのない夜叉神峠ルートを登路とする。夜叉神登山口までは車で上がれる。
県道から登りの林道に入ると監視員の人がいて、ここから先は昼間でもライトをつけるように言われた。ジグザグのきつい、かなりの登りである、夜叉神登山口の駐車場はすでに8割方埋まっていた。朝6時にして日差し強く、標高1370mでも涼しくはない。
登山届を投函して出発する。夜叉神ルートは樹林帯の長い登りなので、それほど人気のルートではない。登山道は他に登る人もおらず、静かだった。
始めのうちは傾斜のゆるい、カラマツ林を背景にした広葉樹の明るい道である。強い日差しが林間に届き体温はすぐに上昇、汗が噴き出す。
広葉樹はミズナラが多い中、ブナの大木も所々で見かける。斜面に猿が一匹だけ佇んでいた。群れからはぐれたのだろうか。
頭上が明るくなって、小屋の建つ夜叉神峠に着く。目の前に白根三山が余すところなく見える。雲ひとつない青空をバックにすばらしい眺めだ。南アルプス南部の山も見える。
小屋番の女性が出てきて、今日は久しぶりに朝から晴れたと言う。峠で休んでいると、下山者がポツポツとやってきた。
夜叉神峠は森の中にぽっかりと空いたオアシスのようで、峠を後にすると再び樹林帯となる。
少しの間は緩い起伏の気持ちのよい広葉樹林で、ブナの大木もある。やがて急な登りに変わり標高を上げても、ミズナラやダケカンバに混じってブナが生えている。
標高1779m、1785mとなかなか立派な大木、しかも樹皮が白い。奥多摩や秩父では、このあたりまでがブナの見られる上限で、これより上は針葉樹となるのだが、ここ夜叉神コースはまだ続いていた。1825mにもどっしりとしたブナがあり、今まで見られたブナの高所記録を更新した。
南アルプスでブナがこれだけ見られるとは思っていなかったが、奥秩父や八ヶ岳に比べて海に近く、ガスにかかりやすく降水量が多いのが影響しているのかもしれない。
林相は薄暗いカラマツやヒノキに変わり、さすがにもうないかと思っていたら、細い高木が1本だけあった。標高実に1930m。こんな高いところで見られるブナはおそらく、日本には他にないだろう。
|
とある文献によると奥秩父の十文字峠(標高2000m)に1本、ブナの大木があるというが、これは鳥が種を運んだものだろうということで、自生ではないらしい。夜叉神ルートの高標高ブナはブナ林とはいい難いが、下部から生育エリアを連続させていてかなり貴重である。
森閑としたシラビソの林に入り、傾斜がゆるやかになって歩みがはかどる。下界の音はなく、セミや鳥の声も遠くで聞こえるのみ。
杖立峠からは一層深い森となる。再び傾斜が強まると頭上が開けた。山火事跡はここのようだ。展望があるとのことだが、樹林の背がそれほど低くないのであまり開放感はない。今日の甲府の最高気温は36度というから、標高2000mを超えたここも暑い。
一泊のテント装備も大して重くはないのだが、このあたりでずいぶん疲労がたまってきた。休み休みの登りとなる。樹林帯の長い登りの中で開けたところに出会えるのはいいのだが、今年の夏は暑くてつらい場所になっている。
石のごろごろした道は次第に平坦になり、シラビソ林に入ってほっとした。甘利山からの道が合流するとすぐに苺平という休憩適地に着く。行く方向が同じ登山者とようやく出会った。
苺平から辻山への踏み跡が伸びていたが、南御室小屋までもうすぐなので先を急ぐ。小屋までは緩い下りの落ち着いた道。途中で辻山への道がもう1本あった。
樹林帯の切り開きに下り着く。南御室小屋は昔ながらの、南アルプスらしい山小屋である。シラビソやダケカンバに囲まれた、ここも深い樹林帯の中にぽっかりと空いたオアシスだ。樹林にはサルオガセが垂れ下がっており、山深さを演出している。
テントを設営する。水場もすぐ近くで1日暮らしやすい場所だ。花は少なくゴゼンタチバナやクルマユリ、また柵に囲まれた小さな斜面にヤマオダマキとテガタチドリが咲いているくらいだ。
このあたりに鹿はいるのだろうか。今日はまだ見ておらず、山が荒れた感じはなく、木の樹皮にも剥ぎ取り跡も見られなかった。山地の鹿の爆発的増加が一時期大きな問題になったが、ここ数年は捕獲量が増え、全国的には少しずつ減ってきているという。
テントは昨年、白山で張って以来。白山は行動終了の時間が遅くただ寝るのみの生活だった。今日は久しぶりにテントでまったりする時間がある。「何もしないをする」、テントの周りをぶらぶらしているのがいいのだ。夜は満天の星空だった。