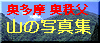翌朝、雲ひとつない快晴である。山で2日間続けて晴れたのはいつ以来だろうか。テントは久しぶりにフライシートが放射冷却でびっしょりになった。

地蔵岳 [拡大]
|
今日は長くなりそうなので、南御室小屋を5時過ぎに出発。朝日がさす前のシラビソ林は、大気も締まって気持ちがいい。
右手から暖かさが感じられるようになるころ、樹林を抜けて砂礫の展望地に飛び出した。標高2700mの森林限界で、砂払岳はこのあたりのことだろう。昨日の朝以来の白根三山や仙丈ヶ岳、そして雲海から富士山が大きく姿を現していた。
薬師岳山荘に下るとダケカンバが地を這うような姿で、頑強に根を張っていた。生命力の強さに心を打たれる。
山荘からは再び砂礫の尾根を登っていく。薬師岳の広い山頂部は、先ほどの2700m点にも増して大展望。奥秩父や八ヶ岳も見えるようになり、初訪時の鳳凰三山の時を思い出した。
タカネビランジはほぼ花期のピークのようで、岩陰を中心にあちこちに白からピンク色のかわいい花をつけている。ややクモイコザクラっぽいものもあり、花弁の形は一定でない。初訪時に見られたホウオウシャジンはまだ時期が早いのか、どこを探してもない。
タカネビランジ以外というとアキノキリンソウやハクサンシャクナゲが見られるくらいで、北アルプスや上信越の山と比べるとやはり花の種類は少ないが、並居る日本の名峰のパノラマ展望がそれを補って余りある。
薬師岳山頂部には、北アの燕岳のように突き立てた様な巨岩が積み重なっており、遠目からは地蔵岳のオベリスクと見間違うこともある。砂礫の山にはこういうイルカの様な岩がつきものなのだろうか。
ところで燕岳の砂礫の斜面に咲くのはコマクサだが、南アルプスにはないようだ。こういう砂礫の地ならどこかに咲いていても不思議ではないが、鳳凰三山はタカネビランジがコマクサの代わりに咲いているような印象がある。
観音岳へは砂礫の稜線漫歩となり、今日の行程で一番快適な部分だ。右手に八ヶ岳や蓼科山が浮かんでいる。岩尾根の登りを経て本日の最高峰、観音岳へ。
岩の累々とした狭い頂上部に上がる。ようやく地蔵岳のオベリスク、そして甲斐駒も視界に入る。甲斐駒のすぐ右、はるか遠くに槍ヶ岳の姿も。
来た方向を振り返ると北岳など白根三山を背景に、夜叉神ルートの尾根がいい形で落ち込んでいた。そこには薬師岳・砂払岳の先、樹林で覆われた辻山がこの尾根の主稜の一角を担っているように、立派な姿で見える。昨日は省略してしまったが、甲斐駒などの眺めもあるということなので立ち寄ってもよかったと思う。
賽の河原へ向かう。途中の鞍部まではかなりの高度を下げ、樹林帯が復活する。カラマツの高山型といっていいのか、スラッと伸びた樹木に松かさ状の実がたくさんなっている。
甲斐駒や地蔵岳がどんどん大きくなる。梯子を使って登りついたところが赤抜沢ノ頭、オベリスクは目の前だ。
砂礫の地に下りたところにはたくさんの石地蔵とともに「地蔵岳」の標識が立っていた。多くの人はここで引き返し、オベリスクまで足を伸ばす人は意外と少ない。自分は基部まで行ってみることにする。展望は他の二山には及ばないが、観音岳の斜面に富士山の姿がよく、絵になる眺めである。
テン場でいっしょだった高校生のワンゲル部のグループが入れ違いで登ってきた。バッグには「都留」と書いてあった。
赤抜沢ノ頭に戻って彼らの行動を見ていたら、オベリスクの裏側に回って一周していた。そういうことができるとは知らなかったが、無駄に危険なことはしない、というのが自分の基本的な山行スタイルなので、知らなくて正解だったかもしれない。
赤抜沢ノ頭からは白ザレまたは岩稜のアップダウンとなり、今までの爽快な登山道からは少し変わる。
無風で日も高くなり、暑さに苦しめられるようになった。標高2700mの地にしてこれだからたまらない。この猛暑日本、夏山アルプスの登山でさえも午前中が勝負になってしまったのかもしれない。
高嶺へは背中あぶりの登りとなり、休み休み登高。甲斐駒方面からの縦走グループといくつも行き違う。皆元気である。東西に細長い高嶺のピークからもパノラマ展望、しかし白根三山はしだいに頭に雲を乗せるようになった。稜線が西に面すると風が通る。少し涼んでから出発する。
今日の核心部はここからだった。高嶺からは狭い岩の間を縫いながらの急傾斜の下りとなる。疲労が来ている時間でこの落ちるような下りは集中が必要。
傾斜が緩んでほっとするが、白鳳峠まではまだ標高差があり、樹林のない岩ガラガラの斜面が続いていた。北岳の眺めは雄大だが早めに日差しがさえぎられる場所に移動したくもある。
ようやくシラビソの林の中へ、すぐ先が白鳳峠だった。ほっと一息ついていよいよ広河原の登山口に向けて下ることになる。
以前早川尾根縦走の時、隣りの広河原峠から下山したときはコースタイム2時間超のところを1時間と少しで下れてしまった。この白鳳峠道も同じようなものかと高をくくっていた感はある。この下りがしんどかったのだ。
まずはさっきの岩ガラガラ斜面の下りの延長が長く続く。この一帯は樹林の発達しない風衝地というのか、樹林に包まれた南アルプスも、下部では北岳の大樺沢ルートのようによくこういうところに出くわす。地形的にもここも昔、沢だったのかもしれない。
「やまなしの森百選」の看板が立つシラビソ林にようやく入る。あまり歩く人が多くないのか、踏み跡があまり定まっていない。尾根状ではないルートは、その場その場で歩きやすいところに道が敷かれているので規則性がなく、方向がめまぐるしく変わって疲れやすいパターンとなる。
途中で大岩を避けての急激な下りとなり、垂直に近い梯子が5段連続していた。
大変な道だが標高は確実に下げ、はるか下に野呂川のゴーゴーという流れも聞こえてきた。それを励みに、足がもつれないように慎重に下る。バスの時間にはちょうどよさそう。
車の走る姿が見え、その車道(白鳳峠口)に下り立つ。前を歩いていた夫婦に大変でしたね、と挨拶する。白鳳峠からは結局コースタイムの2時間かかった。
あとは広河原のバス停まで、15分足らずの歩きである。背後の北岳のてっぺんのほうから、ガラガラトッシャーンと落雷の音が聞こえた。振り返ると山頂部に雲はかかっていたが晴れている。まあ何とかいい天気の中を歩けて、2日間だけだが充実した南アルプス縦走を遂げることができた。
平日にもかかわらず甲府行きのバスは増発されて4台となった。途中の夜叉神登山口で下車し、車で灼熱の下界へ戻ることとする。