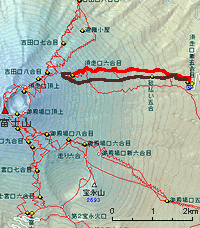
|
 |
2010年8月13日(金)
|
| ◇ |  | 新宿駅 | 6:38 |
小田急線
|
| 7:55 |  | (新)松田駅 | 8:13 |
御殿場線
|
| 8:50 |  | 御殿場駅 | 9:10 |
富士急行バス
|
| 10:10 | 須走口新五合目 | 10:35 |
| 12:00 | 六合目
(長田山荘) | 12:35 |
| 13:05 | 本六合目
(瀬戸館) | 13:15 |
| 14:20 |  | 七合目
(大陽館 泊) | ◇ |
2010年8月14日(土)
|
| ◇ | 七合目 | 5:20 |
| 6:00 | 本七合目
(見晴館) | 6:30 |
| 7:50 | 砂払い五合目 | 8:00 |
| 8:30 |  | 須走口新五合目 | 9:20 |
富士急行バス
|
| 10:15 |  | 御殿場駅 | 10:27 |
御殿場線
|
| 10:50 |  | 山北駅 | 13:59 |
小田急線
さくらの湯立ち寄り |
| 14:07 |  | (新)松田駅 | 14:23 |
小田急線
|
| 15:47 | 新宿駅 | ◇ |
|
今年の春先、のぞむさん・sanpoさんとで富士山に登りましょうという話をしていた。のぞむさんは「望の富士山」というサイトを持っているのに、そしてsanpoさんと自分はこれほど山にしょっちゅう登っているのに、3人とも富士山には登ったことがない。それならいっぺんに登頂しましょう、ということで。
富士山は誰でも登ろうとする山なので、あまのじゃくな自分にとっては今まで、全くの登山の対象外であった。元々見る山であり、登る山としては実際、自分の好みではない。それでも登ろうとするのは、日本一の高い山だから、ただそのこだわりだけである。
山そのものの印象は、思い描いていたものと大きくは違わなかったが、富士山を取り囲む周囲の人工的な環境や、登山者の「なり」に大きな驚きを感じた。

七合目付近の登山道
|
今回は須走コースを登り、七合目の大陽館で一泊。翌日山頂を目指す予定である。
(新)松田駅から御殿場線で御殿場駅へ。そこからバスで一気に標高2000mまで上がる。国道から富士あざみラインまで、今日から3日間マイカー規制とのことで、道は空いていた。あざみラインを走っているランナー集団もいた。
登山口近くなると、駐車場へ入れない車が長い路上駐車の列を作っていた。
 | | 須走登山口 |
 | | 始めは樹林帯 |
 | | 荒れた更地に出る |
 | | オンタデ |
 | | トモエシオガマ |
|
休憩所やみやげ物店が立ち並ぶ須走口新五合目は、残念ながら上のほうがガスで隠されていた。
今日明日と、富士山の天気予報は「曇り時々雨または霧」。ずっといい天気が続いていたのに登る日になってこの空模様。この間の槍ヶ岳のときと同じである。
巨大な独立峰であるこの山の、天気の悪い状況とはいったいどんなものであろうか。天気がいいほうがいいのは当たり前だが、嵐の富士山もちょっと味わってみたい気もする。
支度をして、石段を緩く登るとすぐに古御岳神社。登山道は樹林帯の中につけられており、これはこの須走コースならではのということ。山梨県の吉田口コースは、初めからむき出しの斜面を歩いていくらしい。
山中湖周辺の山と同じように火山帯の特徴である黒土の登山道を緩く登っていく。平日なのに登る人下る人いずれも多く、時には行列になったりもする。
ホタルブクロやオトギリソウなどを多く見る。露岩の目立つあたりではオンタデが群落をいくつもこしらえている。これも火山特有の光景だ。
薄紫の細い5枚の花弁をつけたものを初めて見た。「ムラサキモメンヅル」というらしい。
時折り、樹林が切れて裸地帯に出る。晴れていれば広大な斜面が望まれるはずだろうが、あいにくガスで真っ白。今日は最後までこんな天気だろうか。
しばらくは樹林帯と砂地を交互に繰り返す。ダケカンバが風の力だろうか、斜めになって伸びている。富士山にこんな濃厚な樹林帯があるとは想像外だった。
花もクルマユリ、ハンゴンソウなどが出てくるが、オンタデやホタルブクロはこの後も群落で見られ、他の山のように標高を上げると花の顔ぶれが変わるような感じではない。下から上まで同じようなものが咲いている。
高度を上げるにつれ樹林帯がだんだん少なくなっていくのは、風の強さに関係があるのだろうが、植生に限っては標高によらず均一性が保たれているようだ。
鳥居をくぐった先の長田山荘前で休憩する。案内板によるとここは六合目ということだが、他にもこの先に「本六合目」とか、「元六合目」とかいう場所もあって混乱する上に、いっしょに書かれている標高の数字が、どうも地図上の等高線と合っていない気がする。長田山荘の標識には2450mと書かれているが、地図では六合目の標高は2650mくらいである。
 | | 黒土の斜面 |
 | | ダケカンバ |
 | | 本六合目へ |
 | | クルマユリ |
 | | 頂上部が覗く |
|
雨が落ちてきた。しかし本降りにはならなそうなので、ザックカバーだけつける。さらに登っていくと本六合目で、瀬戸館という山小屋が立っていた。ここが2650mらしい。
このあたりまで来るともう、更地の登りのみ。ガスは相変わらず濃く、ただ同じような斜面を登っていくのみだ。左手に砂走りコースの一本道が見える。この斜度、この斜め具合こそが、遠くから見ている富士山そのものだと実感する。
草地にはオンタデが咲くのみだが、時々クルマユリも見る。ジグザグに高度を稼いでいくと、登りつく先にまた、建物のようなものが見えてきた。今日泊まる予定の大陽館のようである。
ここは七合目。大陽館は、斜面にへばりつくように建てられた、トタン張りの長屋のような家で、戸口の手前にテーブルと椅子がある。椅子は風で飛ばないようにロープで結ばれている。そもそも駅のホームにあるような椅子なので、山には不釣り合いだ。
休憩している人がたくさん。全てが宿泊客ではないようだ。
大陽館の屋根越しに上のほうを見るとガスが切れて、8合目の鳥居と、そしておそらく頂上と思われる平たい部分が見えていた。ここから登りに行く人も、下ってくる人もそれぞれ列が絶えない。
とにかく小屋の中に入る。中は大変狭い。3階まである寝床の1階部分に寝る場所をあてがわれた、
窓がなくほとんど真っ暗である。昼間からヘッドランプが必要だ。こんな採光豊かな明るい場所に立つ小屋なのに、何ということだろう。
枕元にはザックを置いておくスペースがあり、その50cmくらい上のところには木の棚があるので、荷物の置き場所にはさほど困らない。しかしこんなに暗いと、朝出発するとき忘れ物をしてしまいそうだ。
さらに、廊下にもすでに布団が敷かれている。この日の大陽館は、予約なしの宿泊も受け付けているので、これからどれくらい混み合うのか想像がつかない。sanpoさんが小屋の人に、今日の予約はどれくらい入っているのかと聞いたら、それは答えられないと言う。なぜ答えられないのかわからない。小屋の従業員の、何か挑戦的な態度が気になる。
結局どんどん詰め込まれ、廊下にも寝る人があふれ、夜トイレに立つのもままならない有様だ。1人あたりのスペースは幅50cmくらいになってしまい、大変寝苦しい夜となった。
|