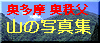|
2021年5月29日(土) |
| ◇ |
 |
練馬IC |
3:55 |
| |
関越自動車道 |
| ◇ |
水上IC |
5:41 |
| |
国道291号
県道63号水上片品線 |
| 6:50 |
|
水源の森キャンプ場 |
7:45 |
| 7:50 |
|
森林浴のみち |
◇ |
| 8:10 |
|
管理車道 |
◇ |
| 8:15 |
|
ヒメカイウ駐車場 |
◇ |
| 8:40 |
|
武尊田代湿原 |
8:50 |
| 9:37 |
|
1700m地点 |
◇ |
| 10:07 |
|
武尊避難小屋 |
10:17 |
| 10:55 |
|
ゼビオス岳 |
11:13 |
| 11:42 |
|
武尊避難小屋 |
◇ |
| 12:05 |
|
分岐 |
12:10 |
| 13:42 |
|
武尊田代湿原 |
13:50 |
| 14:21 |
|
ヒメカイウ駐車場 |
◇ |
| 14:50 |
 |
水源の森キャンプ場(テント泊) |
◇ |
|
2021年5月30日(日) |
| 5:42 |
|
水源の森キャンプ場 |
◇ |
| 5:47 |
|
森林浴のみち |
◇ |
| 6:12 |
|
管理車道 |
◇ |
| 6:27 |
|
ブナの森のみち |
◇ |
| |
ほほえみのみち~ブナの森のみち周回 |
| 7:22 |
|
森林浴のみち |
◇ |
| 7:50 |
 |
水源の森キャンプ場 |
8:08 |
| |
県道63号水上片品線
国道291号 |
| 9:11 |
水上IC |
◇ |
| |
関越自動車道 |
| 10:50 |
練馬IC |
◇ |
群馬県北部・奥利根水源の森へ、今年もブナを見に行く。
今回はキャンプ場で一泊する。ここのキャンプ場はいわゆる登山用のテン場ではなく、駐車場と併用された車横づけタイプのものである。コロナ禍でキャンプブームに拍車がかかり、こういうところは今とても人気がある。
そして今回は、今の車に乗っての最後の山行となる。来月からは新しい車(ただし同車種)に乗り替える。13年間お世話になった今の車に、関東髄一のブナの森で一晩つきあってもらう。

水源の森をバックに [ 拡大]
|
5月28日に林道の冬季規制が解除され、その翌日出かける。関越自動車道を水上まで、この車でもう何十回走ったことか。思い出深い。ICからは藤原ダム、宝川温泉、湯の小屋温泉を経て1時間弱。同じ関東内といっても東京からはかなり遠い。
奥利根水源の森キャンプ場には6時台に着いたのだが、何とキャンプ地はもう満員近い。これにはびっくりだ。みな林道の開通を待ち焦がれていたのだろう。地元の群馬ナンバーばかりかと思いきや、柏や足立、多摩ナンバー、自分と同じ品川もあった。
メインの広場にはあまりスペースがなかったので、少し奥に入ったところに車を停め、すぐにテントを張った。
周囲は瑞々しいまでの若葉色。沢の水量も雪解けで豊富に流れ、野鳥の声がこだまする。天気もまあまあよさそうだ。今日のうちに歩けるだけ歩いておきたい。
沢を木橋で渡り、「森林浴のみち」に入る。緩い斜面を登っていく。
一昨年の同じ時期に来たときはまだ一面の雪で、どこが道かわからなかった。途中まで斜面を這い上がったが結局登るのをあきらめた。そのため今日は念のためピッケルを持ってきたのだが、今年は季節の進みが早く、そんな心配は無用だった。
青空をバックに、すぐに淡緑のブナの森に入る。オオカメノキやカエデなど他の樹種も見かけるが、8割ほどの樹木はブナである。それも高さ10㎝ほどの稚樹から若木、壮年木や大木と、全世代のブナが揃っている。他の山域では普通、ブナは多くても老樹ばかりとか、樹齢に偏りがあるのがほとんどだ。玉原高原のブナ平も、これほどではない。
奥利根水源の森は関東では間違いなく、ブナの生育に適した場所だろう。現在進行形で成長するブナ林である。
尾根の上に上がり、笹原につけられた道となる。倒木が登山道に覆いかぶさっていて、通過に一苦労する。雄花、雌花をつけていた。倒木があると花を見ることができる。
すぐ先で管理車道に出る。雪はなく、もう車で走れそうだ。車道を少し歩いて武尊田代への登り口のあるヒメカイウ駐車場に着く。すでに車が4台停まっていた。登山道に入ると、再び倒木が道を塞いでた。
林道開通が昨日だから、今年になってここを歩いた登山者はまだ数えるほどしかいないはず。倒木などで荒れていても不思議ではない。その割には登山道そのものは歩きやすく、崩れているところもない。
このあたりは新潟県魚沼地区と緯度的に同じくらいの位置にあるが、上越国境稜線によって日本海からの豪風雪からガードされているため、魚沼ほどの多雪地域にはならない。そのため登山道も思いのほか安定している。
もっともこの冬の始め、水上町藤原地区では記録的な積雪を記録したため、雪はそこそこ残っているかと思われたが、今のところ道脇にわずかな残雪しか認められない。
相変わらず全世代型のブナの森が続く。葉は大きく、スマホを裕に隠してしまうものもある。緩く登っていくとシナノキの高木に今年も出会う。周りのブナがこれほど葉が開いているのに、シナノキだけはまだ芽吹いたばかり前だ。ダケカンバもまだ芽吹いていない木も多い。
木道が現れ、武尊田代湿原に着く。湿原と言っても、花の時期はまだ先で、特に見るべきものはない。この先にヒメカイウが咲く言う場所があるが、まだ見たことはない。
ここから先は武尊山避難小屋まで、標高差100m強、1時間半くらいの緩々の登りである。ブナの森は密度を増し、どんどん深くなる。以前は6月に2度歩いたが、5月末だとやはり緑は軽く柔らかみがあり、今がまさに新緑たけなわだ。
若い人が一人、早足で歩いて行った。おそらく武尊山まで往復するのだろう。
少し天気が悪い方向に向かっている。目指す稜線方向は風が強そう。自分は武尊山までは行く気はないが、眺望も楽しみたいので、せめてゼビオス岳付近まで登りたい。
針葉樹が現れるあたりが標高1700m付近。この森は植生分布がはっきりしていて、針葉樹を見た後はブナはぱったり見られなくなる。新緑瑞々しい落葉樹の森から、黒木の目立つ高山の雰囲気に突然変わるのが面白い。稜線に上がるまでに見られる針葉樹はほとんどがシラビソで、オオシラビソではない。
残雪が現れた。平尾根なので、ちょっとぼやっとしていると方向を見失ってしまう。先の人がつけたと思われる。小さな足跡が雪面上にあるので、これがいい目印になった。
少しのアップダウンののち、ようやく視界が開けて稜線へ。武尊避難小屋に到着する。この辺りの針葉樹はオオシラビソに変わっている。ここで携帯の電波が届いた。水源の森キャンプ場一帯は携帯の圏外で、ここで一泊することは、スマホ通信のない、一昔前の生活スタイルで一晩過ごすことを意味する。
稜線は思いのほか天気はよく、奥日光や足尾の山、赤城山などがよく見える。武尊山方向へ少し歩いていく。木の間から武尊山の姿も見えてきた。北側には越後三山と思われる、残雪豊かな稜線も視界に届く。久しぶりに標高1800mを超えるところまで登ってきて、気分が少し高揚してきた。残雪の上を歩く場所もまだかなりある。
背後の見通しがよくなり、小ピークに着く。山名表示はないがゼビオス岳である。水源の森からの往復なら、ここらあたりが1日コースとしてはちょうどよい距離である。
朝早かったので、時間的には武尊山まで行けそうだが、かなりハードな行程となる。自分にはもはやそこまでエネルギーを絞りだして歩く気はない。
ゼビオス岳からは燧ヶ岳、至仏山、笠ヶ岳がよく見える。ここから眺める尾瀬は、高層湿原が周囲より一段高くなっているのがわかるので面白い。
来た道を下っていく。避難小屋からはさらに直進、武尊田代へ戻るもう1本の道を使う。変化の乏しい樹林帯の下りが続く。分岐を見落とすと武尊牧場まで行ってしまうので、見逃さないように注意する。避難小屋から20分ほどで分岐となった。
こちらのコースは沢を何回も渡り、登り返しもそれなりにある。明るい斜面は先駆種のダケカンバ林となっている。ブナやミズナラなどの大木と違い、ダケカンバはせいぜい50年前後しか生きていないという。今後この森がどう変化していくか興味深い。
また、さっきの登りの道と比べて、少々ヤブっぽいところもある。ゼンマイがたくさん伸びていた。
コースタイム50分のところを1時間30分もかけ、武尊田代に戻る。あとは往路と同じ道を下って、水源の森キャンプ場に到着となる。
キャンプをしている人は家族連れが多く、テントのほかターフを張っている人もいる。焚き火台もある。薪用の木を探している人を見かけるが、このあたりは火付きのいい針葉樹がないので、苦労しているのではないか。
登山用の軽量テントは自分のほかあと一人くらいしかいなく、完全に浮いている。ここは山小屋どころか、管理棟も売店もない、ただスペースがあるだけの場所だ。この豊かな自然に惹かれて皆やってくるのだろう。
食事がてら、家から持ってきたビールとウイスキーを飲んでると急に酔いが回ってきて、いつのまにか寝てしまった。
------------------
夜は曇っており星空は見られなかった。朝、野鳥のさえずりで目を覚ます。空も次第に青い部分が増えてきて、今日もそこそこいい天気になりそう。
今日は忙しい。今の車の車検が今日で切れるのだ。帰ったらその足で、ディーラーに下取りに出しにいく。そのため、キャンプ場をお昼前には出たい。
テントを先に撤収して車に収める。ふたたび森林浴のみちを登り、近くのブナの森のみち(遊歩道)を一周してする。こちらのブナの森もすばらしい。クロベが混ざっているのも興味深い。受粉を終えたブナの雌花が見られた。
帰路、この車との長旅もこれが最後となる。
2008年、初めて今の車を中古で買い、奥多摩の生藤山に初のマイカー山行をした。それ以来もう、300回くらいはこれで山に行っただろうか。車中泊は80回近くやったし、北アルプス、南アルプスもこれで行った。遠くは山形県の飯豊や福井県の荒島岳、岐阜県西部の能郷白山まで足を伸ばした。軽自動車だが、実力以上によく走ってくれた。軽でもターボエンジンなので、比較的長距離のドライブがこなせたと思う。
トラブルもいろいろあった。東北道を走っていてバンパーが落ちそうになったり、赤城高原SAで車中泊した翌朝、バッテリーが上がっていたり、釈迦ヶ岳(御坂)の登山口では未舗装林道の溝にはまって動けなくなり、レッカー車のお世話になったことも。今となっては楽しい思い出である。
山に行くのに車を使うことには、議論があると思う。公共交通機関で行くのと比べれば、自然環境へのダメージは明らかに大きい。人間にとって本来、山は「遠き遥かな」存在だったのだが、車は人と山の距離をぐんと縮めてしまった。人間が容易に自然に足を踏み入れる機会を格段に増やしている。
コロナウィルスがあっという間に全世界、日本全国に広まった原因も、人の移動を容易にした車の存在は小さくないだろう。
山行そのものに対する考え方も変わった。電車・バスで山に行ってた頃は、時刻表という制約事項があるため、とにかく計画を綿密に行い、頭の中で何度もシミュレーションしてから当日を迎えたものだった。電車に乗っている間も計画を考え直したりする時間もあった。とにかく最初から最後まで密度の濃い山行になっていたと思う。
マイカー山行は計画が短時間で容易に組み立てられることで、山行そのものに対する思い入れ度が少し薄まった気もする。
しかも車は、金がかかる。購入代金よりもむしろ、買った後だ。ガソリン、オイル交換、定期点検、修理、車検、そして自動車税、自動車保険。タイヤは5,6年ごとに買い替えが必要になるなんて知らなかった(乗らなくてもゴムが劣化するので買い替えは必要)。家計への圧迫も半端ではない。
もし車を持っていなかったら、経済的にどれほど楽になっていたか。所詮車は贅沢品で、金持ちの道楽なのだ。
車を持つのをやめる理由はこのようにいくらでもあったのだが、それでも自分は車と縁を切ることはできなかった。電車・バスで行ける山しか登れない、そういう登山ライフには今さら戻れない。麻薬のようなものである。
買い替える車も同じく中古の軽だが、昨年(2020年式)のものなのでほぼ新車である。外観や装備の贅沢さは前の車の比ではない。スマアシという、運転支援システムも一部搭載されている。
年齢的に、もしかしたら自分にとっては最後の車になるかもしれない。なるだけ運転が楽に出来るものがいいと思い、少し奮発してしまった。
帰り道の関越で、走行距離がついに15万キロを超えた。そのうち自分が乗った分は12万キロくらい。それでも地球を3周したことになる。
狭い国土の日本だが、まだ行ってない山はたくさんある。体力の許す範囲で、運転のできる範囲で、これからもほうぼうの山を巡りたい。