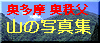梅雨明けして最初の週末は天気がよさそう。八ヶ岳は昨年行ったので、今年は谷川連峰にする。
蓬峠へテント泊に行く。もう何度も行っているが、今回は天気が保証付きということもあって、期待は大きい。
巷では緊急事態宣言、そして東京オリンピックと気ぜわしい。いつも以上に人との接触を極力避けることを心掛ける。
今年のテントは2回目だが、1回目は車横づけの、登山とは言えないものだった。重荷を背負ってのテント泊は今年初となる。

登山道は笹に埋まり、地面が見えない [拡大 ]
|
買い替えた車で初めて関越を走り、湯沢で下りる。土樽の茂倉岳登山口には6時半に到着。駐車場にはすでに7,8台ほど停まっていた。
6時台なのにもう日差しが強い。しかも紺碧の空。ついこの間までのジメッとした空気はない。いつの間にか正真正銘の夏がやってきた。
久しぶりの重い荷物を背負い出発。少し下った後、単調な林道歩きが始まる。人工林に入るとしのぎやすいものの、明るい河原沿いに出るたびに汗が噴き出る。
歩き始めて20分ほど、途中のスペースに車が数台、停まっていた。八王子ナンバーなので林業従事者の車ではなく登山者か。いつも茂倉登山口に車を停めていたが、蓬峠に登るのなら、ここまで車で入れると、林道歩きが省略されて有利だ。しかし認知された駐車スペースなのかはわからない。
林道終点から登山道に入り、水場のある蓬新道入口へ。水の染み出す湿っぽい登山道となる。
途中で河原を歩くが、直射日光を浴びて暑い。その先、登山道崩壊のため、スチール製の梯子のついた高巻き道を利用する。
東俣沢出合に着く。沢を渡るときに足を置いた場所が悪く、靴に水が入ってしまった。これは大変と思ったが、10分ほど休憩しているうちにほとんど乾いた。
登山中に靴に水が入ると、ふだんならしばらくはびちゃびちゃしたままで歩くことになる。梅雨明け直後の日照りと乾いた空気のなせる業か。
ここからは登りになる。沢音の聞こえる方向が次第に低くなり、野鳥の声が響く静寂な森の道になる。
緑深く、直射日光が遮られる。しばらくこのままの道であってほしい。
ブナの木の根に乗って写真を撮り、下りるときに足を踏み外して膝のすぐ下を強打してしまった。出血してズボンにも小さなカギ割きができる。注意力の散漫さがこしらえた傷だったが、脚力の衰えを感じる。不安定な場所でのバランス力も最近は鈍り気味である。
痛みはそれほどなく、歩くことには問題がない。膝のお皿でなくてよかった。ジグザグの登りから中の休場、さらに登っていくと次第に周囲が開けてきて、チシマザサの稜線が見えるようになる。
小さな沢といくつか越えるうちに、右後方の眺めも広がる。苗場山など上信越の山々も青空の下。開放感のある眺めはすばらしいが、直射日光を浴びるとつらい。麓の気温が30度を超えると、標高1000数百メートルくらいの山では、課題はやはり暑さだ。
同時期によく行く八ヶ岳は、登山口が蓬峠の標高くらいなので、その点では楽である。
花はアカモノやサンカヨウはいずれも結実、他にはクモマニガナくらいしか見られない。賑やかになるのは稜線に出てからとなりそう。
さっきのこともあるので、ガレたところは慎重に足運びする。最後の水場に到着。テント用の水は後で汲みに来ることにして、そのまま歩く。トレラン姿の人とすれ違う。
ここから峠までの緩い登りがすごく長く感じた。久しぶりの重い荷物で、暑さもありかなりへばってしまっている。クルマユリ、オオバギボウシ、ノアザミが咲いていた。
蓬峠に到着する。テントはまだ張られていない。空は真っ青、すばらしい展望。谷川岳や一ノ倉岳などの主脈はもちろん、赤城連山もくっきり見えた。小屋の前で休憩してからテント設営する。
稜線は南風が強く、日差しギラギラだ。テントの中は蒸し風呂状態。むしろ外で風に当たっていた方がしのげる。
水を汲みに行き、テントの申し込みをする。明日の予定を聞かれたが、特に縦走するつもりもないので、そのへんをぶらつくだけです、と言ったら怪訝な顔をされた。とりあえず、武能岳往復と書く。買った缶ビールは新潟限定販売のものだった。
体力が回復したので、ビールを飲んだ後だが少し歩くことにした。七ツ小屋山方面へ、笹の稜線を行く。
刈払いがあまりされておらず、地面が見えないところもある。高山植物は多く、ニッコウキスゲ、シモツケソウ、ハクサンフウロ、タテヤマウツボグサ、ミヤマシシウド、キオン、ヨツバヒヨドリなど、色も姿かたちもバラエティに富んでいる。シシゴヤの頭への分岐点で引き返す。
以後、蓬峠のテントは10張り近くなる。ここにしては盛況だ。スペースはふんだんにあり、おそらく20くらいは張れるだろう。
夕刻、久しぶりに日没の太陽を見た。西の空が真っ赤になっていた。
-------------------------------
朝日は朝日岳の左側、尾瀬方面から上がってくる。
昨日、コンロのガスを切らしていた。またやってしまった。隣のテントの人に借りることもできたが、今日はパンだけで頑張ることにする。
他のテントの人はほとんどみな縦走するようで、暗いうちから出発した人もいた。自分の心の片隅にあった、茂倉岳を越えての周回コースは、ひざ下を打撲したこともあり、大事をとってやめる。予定に書いたとおりに、武能岳を往復することにした。
今日も一転の雲もない、快晴。しかし風がないので、日が高くなる前には往復してしまいたい。
こちらの登山道も笹刈りがされておらず、地面が見えない。しかも笹が朝露で濡れており、普通のズボンで歩くとびっしょりになってしまう。アザミの棘もチクチクして煩わしいので、雨具の下を履いていく。しかし、それでも靴に水が入ってしまった。
雨具は体を濡れから守ってくれるが、足回りにはあまり効果がない。雨具の下を履いていても、さらにスパッツで足首を保護することが必要と感じた。
一面の笹原には、高山植物が昨日にも増して多く見られた。昨日見たもの以外にはクガイソウ、タカネコンギク。上の方にはキンコウカも咲いていた。
上部の稜線に出ると、茂倉岳の奥に万太郎山や仙ノ倉山も姿を現し、谷川連峰の主役がすべて揃う。この先きつい登りはなくなるが、ガレたところは慎重に歩を進める。
そして武能岳に到着する。360度の大パノラマは言うことなし。奥日光や皇海山など足尾の山も見えるようになった。
この先、荷物がなければ行ってしまいたくもあるが、テントをしまいに戻らねばならない。下りしな、蓬峠を見下ろすと、自分のテントだけがとり残されていた。
強打した膝は、下りは大丈夫かと少し不安だったが、普通に歩くことができた。これならテントを背負っての下山も大丈夫だろう。蓬峠に下ってテントを撤収、小屋の横で展望に別れを告げ、下山にかかる。
日が高くなると、今日も昨日同様、日照りの地となった。違うのは風がないこと。これで昼間が無風状態だと、日除け場所のない蓬峠でテント設営はかなり厳しいのではないか。熱中症になりそうである。
ブナ林を下っていくとき、登りの人と何人もすれ違う。ヒュッテに泊まるという中高年の人が多い。熱中症に気をつけてと声をかけていく。
東俣沢出合で下りは一区切り。暑さに苦しめられながらも最後の登山道を歩ききり林道に出る。関越自動車道のシュー、シューという車の音が聞こえてきた。茂倉登山口に戻って一泊二日の山行が終わった。
今年の夏は4年ぶりに、北アルプスにテントで行きたい。今日はそれの予行練習のつもりでも来たのだが、気候条件がずいぶん違うのであまり比較にはならないかもしれない。
しかし、体力そのものは4年前と比べてもはっきり落ちてきているのがわかった。今までのような北ア登山を望むのは少しハードルが高すぎるかもしれない。悩むところである。