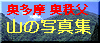夜中起きてみると、空には星がほとんど瞬いていなかった。朝4時半起床。空は厚い雲に覆われていた。
食事をしている間に、他のテントはもう出発してしまった。今日の行程は皆長いのだろう。自分は今日、時間に余裕があるのでゆっくりできる。
6時に蓬峠を出発する。

ニッコウキスゲ咲く稜線から群馬側を見渡す。正面遠くに赤城山を望む
|
放射冷却がなかったせいか、気温はそう下がらず、笹も露で濡れていない。ヒュッテ後ろの高台に上がると、赤城山が雲海の上に浮かんでいて幻想的だった。
日が差さないとニッコウキスゲは花を開ききれないのだろうか、半開きのものが多い。七ツ小屋山に向かう道にはタテヤマウツボグサが多く見られ、クルマユリも咲いていた。
シシゴヤの頭への分岐を見て笹原の道をさらに進む。木道のつけられた湿原状の場所に下るとキンコウカが目立ち始め、ムカゴトラノオが風に揺れていた。この前後もニッコウキスゲが咲き続けていた。
七ツ小屋山山頂に到着。山頂から清水峠にかけては、国境稜線で一番北側に位置する。そのせいか、新潟側から涼しい風がやってくる。特徴ある大源太山が大きく見える。そしてその先には湯沢あたりの町並みと、遠くには魚沼平野も見渡せた。
清水峠へは急坂を含め、少し歩きにくい道になる。笹も深く、清水峠への下りは、建物が見え始めた後もけっこう長く感じる。
清水峠に着くと、今日も新潟側から青空がにじみ始めていた。それと同時に気温も上がる。下山地はそれなりに暑そうである。初夏の笹原の風景や谷川連峰の眺めを見納め、下山にかかる。
居坪坂は10年前に歩いている。始めは馬道と言って斜度のない、のんびりした道。しかしここもそれほど整備が入っているようには見えなく、やや草深い。倒木が処理されず残っている。
樹林の間から清水峠や大源太山が覗く。時折り現れる石畳が昔の街道の面影を残す。その後ブナ林のジグザグの坂道となるが、峠道らしく歩きやすい。
なお、このジグザグ道の前にあった案内板の場所に旧国道のかすかな道形が分岐していたそうだが、見落としていた。
初めのうちはかすかだった沢の音も次第に大きくなり、登山道が湧き水で洗われるようになると登川上流に下り立つ。広がってきた青空を見上げながら休憩する。沢沿いであっても、やはりあの涼しい草原から降りてきた身には、急に気温が上昇した印象である。
道は再び平坦となり、登川から少し距離を置きながらの樹林の道を行く。小さな滝をまたぎ、それ以降も小沢いくつか見る。水の補給には苦労しないルートだ。
やがて鉄塔のある場所に出る。この付近が兎平というところで、少し先に行くと案内板があった。この道は明治時代中期、旧国道が崩落で使えなくなった後、民間人が独自に切り開いた有料道路だったそうである。当時は宿泊所や茶屋も建てられけっこう賑わいを見せたようだ。
清水峠からのもう1本のルート、十五里尾根は上杉謙信が上州進出の際に用いた軍道である一方、こちら居坪坂コースは物流や文化交流で栄えた道のようである。
左下方に河原を見ながらの山腹道が続く。読売新道の奥黒部ヒュッテからの水平道を思い出すが、そう危険なところはなく、やがて河原に下りる。赤ペンキにしたがって対岸に移る。付近は護岸工事中で、ここからは工事用の林道を少し歩くことになる。近くに登山者用の休憩所がある。
清水集落と書かれた木の標柱を見る。林道をそのまま行きかけたが思い直し、標柱の所に戻って周囲を確かめたら、草むらの中に踏み跡がうずまっていた。
前回も河原に下りたところまでは覚えているが、その後どうやって山道に戻ったのか。こんなところを入ったのだろうか、全く記憶がない。
踏み跡に入ると、やがて道ははっきりしてきたので、これでよかったのかと思う。しかしすぐに大きな崩壊地。上部の林道付近から大きく崩れ落ちてきている。うっかり入り込むと滑落しそうだ。
高巻いて何とか反対側に移るが、すぐ先の滝で道は寸断していた。いったん滝の中に下りないと進めないが、その先に続いている踏み跡に登れそうもない。
無理は出来ず、ここは退却する。他に登山道はないようなので、引き返してさっき分かれた林道を下ることにした。
青空と日差しが復活し、汗をかきながら工事用の林道を淡々と下っていく。日曜なのでトラックなどの行き来はない。
登山道より回り道になるかと思ったがそれほど時間のロスもなく、河原の登山道に合流した。そこは十五里尾根との合流点よりかなり先のようだった。
それにしても、10年前は崩壊などなくすんなりと歩けた記憶である。もっともあのときは、工事中の人が登山道で進路案内していたので、何か別のルートで通り抜けていたのかもしれない。
で、その後清水へも思ったほど時間はかからなかった。バス停のある清水集落に到着。巻機山が青空に映えている。バスの時間まで1時間以上ある。ここは久しぶりに「山菜だらけそば」を食べていくことにしよう。
上田屋食堂の本棚に興味深い冊子があった。「越後国南魚沼郡 清水林間学校資料」というもので、東京江戸川区の中学校が昔、ここで林間学校を行った際に作ったと思われるガリ版刷りの本である。
旧国道の歴史はじめ、今日歩いてきた居坪坂や三国峠、また清水トンネル開通の経緯などの出来事が、写真や新聞記事を使って紹介されていた。
中でも、昭和36年、上越線の新清水トンネル建設計画の新聞の記事の切り抜きが興味を惹いた。土合駅が地中駅となったのは、このトンネルにより上越線の全線複線化が実現したときであり、それ以前の単線のときは今の上り線の地上駅に、下り線も乗り入れていた。大昔からトンネルの中ではなかったのである。日本一のモグラ駅は日本の鉄道近代化の産物だったのだ。
なお、今回の山行記に記した史実の一部は、この資料から引用させてもらった。
バスの時刻なので腰を上げる。表はすでに炎天下の中。バスはバス停に停まっていて、運転手さんは後部座席で昼寝していた。
のんびりした田舎の風景を見ながら六日町駅までバスで行く。