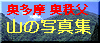翌朝はやや雲の多い空。風が強く甲斐駒や仙丈はすごい勢いで流れる雲で、見えたり隠れたり。
今回は小太郎山に登る目的でやって来た。肩の小屋からなら、小太郎山経由でも時間的に問題なく下山できる。
しかし昨日北岳へ登った疲労感が抜け切れていない。足首と膝は大丈夫だがいつ痛くなるかわからない。往復3時間近くかかる小太郎山に行けるかどうか自信が持てず、とにかく小太郎山分岐まで行って考える。

標高の低いところにある防鹿柵では、高山植物の植生は戻っていない
|
テントをしまい、小太郎尾根を引き返す。曇っていても見通しは良好だ。
小太郎山分岐に着き小太郎山まで続く稜線を見る。伸びやかでな尾根の先に小太郎山が意外と近くに見え、1時間以上かかるような気がしない。心が動くが、やはり体力と足の具合を考え、今回はこのまま草すべりを下山することにした。
下山は大樺沢方面へ。シナノキンバイ群落を抜け、昨日苦しめられた御池からの登山道を分けると、しばらくしてお花畑は規模が小さくなった。ダケカンバの多く茂る広々とした谷間の道は、上部に北岳バットレスが大きく見上げられる。
高度を下げるにつれ気温は上がり、高山植物の顔ぶれもタカネグンナイフウロ、カワラナデシコなど中亜高山のものに変わってきた。
残雪が出てきて、再び防鹿柵のあるお花畑が現れる。しかしこちらは草すべり上部と違って植生はあまり復活していなかった。柵の中も外も同じような状態である。
このあたりは傾斜も緩く、柵があるとはいえ野生動物が入り込みやすくなっているのだろう。また気温や降水量といった気象条件による植生変化も、標高が低いところほど顕著に現れているとも考えられる。
12年前、9年前との比較しかできないのではっきりとしたことは言えないが、南アルプスのお花畑が後退したのは、本当に野生動物による食害が第一要因なのか。今回見た限りは柵の内も外もそれほどの違いはなく、むしろ場所または標高によって大きな差があった。やはり気候変動が大きな原因になっているのではないだろうか。
気温の上がった所は裸地化が進み、本来なら生育に厳しい、標高の高い場所に高山植物は生息地を移していっているいるように見える。
ダケカンバ林を下っていくと、大樺沢の雪渓の上につけられた明るい登山道となる。八本歯から雪渓を下ってくる登山者も見えた。大樺沢二俣で登山道は合流し、さらに白根御池からの登山道を合わせる。このあたりでミヤマハナシノブも見納めである。
まだ残りは長い。すぐ下に雪渓が走っているので暑さは緩和される。平日にもかかわらず、登ってくる登山者は多い。
高度を落とし、橋を渡るころには、雪渓はいつしか勢いよく流れる水に引き継がれていた。登山道にも水が流れ、水面がキラキラ光る。振り返ると空は深い青色となっていた。
樹林帯に入ってしばらく行くと、昨日登った白根御池ルートと合流、すっかり天候回復した中を20分ほどで広河原山荘の前に出た。広河原のバス停に戻って山のほうを見上げると、昨日は見えなかった北岳の稜線が輝いていた。
平日であるが、帰路も乗合タクシーの運転手さんはスタンバイしており、路線バスの定刻より早く広河原を出発する。芦安で下車すると、2日ぶりの暑い夏が待っていた。
この日甲府の最高気温は36度を超え、中央自動車道は灼熱の地。カーエアコンの効きの悪さにいらついていたが、そのうち空が暗くなり、あっという間に大雨に。ワイパーを最高パワーにしても前が見えづらく、大変な帰路となってしまった。
高速道路は路面の下に速度センサーが埋め込まれており、走っている車の速度が遅くなるとそれを渋滞と判断し、交通情報で流される。この日は大雨のために車は軒並み時速40キロ以下のノロノロ運転となり、混んではいないのに渋滞マークがつくという珍しい現象となった。
それにしても猛暑の夏空から一転して大雷雨、今年は各地で極端な天気が続いている。