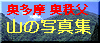何度か目を覚ますうちに、東の空が白み始める。テント場も次第に物音があちこちで聞こえるようになる。
そして鳥のさえずりがまず一つ、それに応えるように別の方向からまたひと声。
ベンチレーターから外を見ると、周りの稜線が見えていた。外に出たら昨日は見えなかった槍の穂先が目の前に。振り返ると白く透き通った空の下、安曇野が一面の雲海になっていた。

朝の蝶ヶ岳から。槍ヶ岳~奥穂高岳の稜線がくっきりと
|
多くの登山者とともに日の出を待つ。地平線のかなり手前の雲海の中から、真っ赤な太陽が出てきた。不思議な光景である。振り返り見る槍・穂高もみるみる赤く染まっていく。
しばらくして地平線から本物の太陽が出て、先の雲海からのものと同化した。どういう仕組みでこのように見えるのか、よくわからない。
とにかく今日は、朝のうちは展望の稜線歩きができそうである。昨日の霧の夜がずっと続いていたらそのまま横尾に下山、ということも考えていた。いくら今日の後半(大滝山~徳本峠)が眺めのない樹林帯の登山道と言っても、やはり青空の下で歩きたいのが本音である。
蝶ヶ岳ヒュッテもようやく荷揚げのヘリが飛び、従業員さんが忙しそうに玄関前を行き来していた。
槍穂の展望台、瞑想の丘でつい長居してしまい、出発が6時を過ぎてしまった。テント場の裏手から歩き始める。安曇野の雲海が眩しく、日焼けしそうである。
しばらくは三股への下山路を下り、途中で大滝山方面の道に分岐する。このあたりは草付の斜面となっており、お花畑が発達している。昨日から見られたハクサンフウロ、クルマユリに加えてウサギギクの群落、ヨツバシオガマ、イブキトラノオ、シラネセンキュウなど種類も豊富である。
花が終わったばかりのチングルマは、綿帽子がまだ尖っている。潅木帯に入るとキヌガサソウがあったが、これも花は終わり近い。
標高をどんどん下げ、いったんコメツガの樹林帯に入る。少し登り返すと登山者が3名やってきた。大滝山荘に泊まったそうだ。池塘の点在する湿原を歩く。正面に大滝山と思われる山体を見ながら鞍部に下る。その大滝山へ、傾斜はきつくはないが長い登り返しとなる。草原と樹林帯を交互に繰り返しながら高度を取り戻していく。
振り返ると、長塀尾根を前景にして穂高連峰が姿を現していた。蝶ヶ岳の後ろにも槍、常念岳の姿も再登場している。森林限界を越え、ハイマツと白砂の眺めいい稜線に出る。オゴジョかテンか、よくわからなかったが胴長の小動物がいた。
眺めはさらに開け、焼岳から乗鞍、御嶽山も。安曇野から松本方面の市街地が、薄くなった雲海を透かして見下ろせた。進む方向の大滝山は下部が樹林、上部がハイマツに覆われていた。
鍋冠山分岐から数分で大滝山北峰に到着する。ハイマツ越しではあるが今までと同様な展望が得られる。大滝山付近は、アルペン的景観と緑がミックスした自然豊かな環境が保たれ、雲ノ平や双六~弓折岳あたりと共通するものがある。
常念岳方面には早くも雲が湧き立ちはじめていた。今日も天候の変化は早そうである。
潅木の中を数分で、大滝山荘の前に出た。小屋から物音は聞こえるが、テントも張られておらず静かである。朝でも大いに賑わっていた蝶ヶ岳ヒュッテからここにやってくると、ホッとしたような、何か寂しいような印象だ。徳沢へ下りる道が通れないので、アプローチの長い大滝山登山は敬遠されているのだろう。この間の道が使えれば、蝶ヶ岳と大滝山を徳沢から結んだ手ごろな一泊コースができていいのだが。これから歩く徳本峠を通るコースはあまりも長すぎる。
さらに10分足らずで大滝山南峰。2000年アルペンガイドには、山頂から槍ヶ岳の眺めが広がる写真が載っているが、その写真に比べると今はハイマツがすごく伸びていて、展望が得にくい。山頂に転がっている石の上に乗ると何とか見られる。ハイマツという植物も、10年以上経つとこんなに伸びるものなのか。
南峰から、そのハイマツの中につけられた道を下っていく。すぐに南東面の日当たりのよい急斜面につけられた道になる。ここも高山植物が多い。しかも今まで見た顔ぶれとは様変わりで、タカネナデシコ、シモツケソウ、タテヤマウツボグサ、ヤマハハコ、ミヤマコウゾリナ、シロバナニガナなど、亜高山でよく見かける種が次から次へと出てくる。さらにニッコウキスゲ、マルバダケブキ、ミヤマシシウドなども。
安曇野方面の眺めもよく、鍋冠山からの長い尾根道が一望された。鍋冠山は、三郷スカイライン展望台から大滝山への登路の一ピークだが、ゆったりこんもりした図体が面白い。
奥多摩の大岳山も鍋冠山という別名を持つが、あちらは取っ手の付きの鍋の蓋の形で、この信州の鍋冠山は鍋本体、それも中華鍋である。
登山道は再びオオシラビソなどの森に入る。これからしばらくはひんやりした樹林帯の中を歩くことになりそうだ。当然雰囲気がガラッと変わり、汗がスッと引いた。歩く人はおそらくそう多くはないと思うが、道はしっかりと整備されている。
急な下りのないまま変化のない道が1時間、1時間半ほど続いた。単独の女性を含め、数名の登山者とすれ違う。
ここは静かな山志向の人には、じっくり登れる道として好まれそうだ。そしてこの日の差しにくい登山道にも、ゴゼンタチバナなどの花が咲き続いている。場所を選ばず花が多いのは、さすが北アルプスである。
緩やかな登り返しも交えて、いったん鞍部のような場所に下る。地図を見ると、次の大滝槍見台までは標高100m以上を登ることに気づいた。
「大滝」と名がついているので、てっきり大滝山の下り途中にあるものと思っていたが、実際のところは、徳本峠から大滝山へ至る途中のいくつかのピークのひとつ、と捉えたほうがいい。そしてこの登り返しは急登だった。あらかじめわかっていなかっった登り返しほどつらいものはない。
息を切らしてその急登をこなすが、その後もだらだらした緩い登りが長く続くので、精神的につらい。
40分ほどの登り返しでようやく大滝槍見台に着く。木製の櫓は上るのにちょっと勇気がいるいでたちだが、造りはしっかりしていた。傍らに材木がたくさん転がっていたので、何度か作り直しているのだろう。
二段ベッドについているような垂直の梯子を登ってみるが、上からの眺めは一部樹林にじゃまされていた。しかもこの時間はすでに雲が多くなっていて、アルプスの山並みはぼんやりしたものだった。
似たような地形、登山道が続く。下って再び登り返し。明神見晴はその登りの途中にあり、表銀座方面の稜線を望むことができた。
朝の蝶ヶ岳から比べるとずいぶんと気温も上がってきている。再び樹林の中の登り下りが続く。下り一方になるとようやく建物の屋根が見えてきた。待望の徳本峠への到着である。時間以上に長く感じたが、意外と楽しめた道でもあった。
徳本峠は北アルプスでも代表的な峠であり、新島々からの登路は、上高地が開かれるずっと前から使われていた歴史ある峠道である。日本アルプスの父・ウェストンもこの峠道を通って槍・穂高を目指している。自分が北アルプスに初めて登ってから17年、ようやくこの峠に立つことができた。
徳本峠小屋に泊まる人、霞沢岳を往復する人などで賑わっている。テントも張られていた。今日は明神に下るが、ここに泊まるなら新島々からの峠道を登ってきたいものである。
明神へは沢を見ながら、また時折り枝沢をまたぎながらの道となる。よく整備されており歩きやすい。沢が見えるところにはセンジュガンピがどこまでも咲き続いている。今回は尾根、森林限界、湿原、最後に沢沿いと、2日間でいろいろなタイプの道を歩いたため、見た高山植物も実にバラエティに富んでいた。
林道に下りる。半袖のTシャツに着替えていく。明神分岐から明神に戻ってくる。午後の高い日差しを受け、遊歩道の歩きでは体にかなり疲労がたまっており、なかなか足が前に進まなかった。
それでも人で溢れる上高地に14時半に到着。30分に1本のバスでさわんど大橋に戻った。さわんど温泉の熱いお湯で2日分の疲れを洗い流し、北アルプスを後にする。
2日間だけだったが、槍穂高の眺め、豊富な高山植物、深い針葉樹林、どれもが目に鮮やかに焼きついた山行だった。